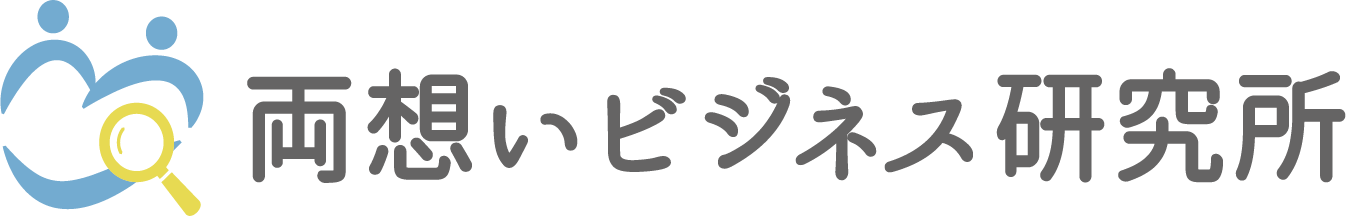経営者が“自分自身と両想い”になると何が変わる?「両想いビジネス」3つのメリット

「頑張っているのに、なぜか報われない」
「成果を出しても、心が満たされない」
「社員やお客様のために尽くしているのに、どこか孤独だ」
そんな声を、これまで数多くの経営者の方から聞いてきました。
その背景には共通点があります。それは、「自分自身との関係がうまくいっていない」ということ。
どれだけマーケティングを学び、経営戦略を磨いても、自分との関係が整っていない経営は、必ずどこかで歪みが生まれます。
今回は、「自分自身と両想いになる」と何が変わるのかを、具体的な3つのメリットから解説します。
経営者が“自分自身と両想い”になるとは?
他者との関係の前に「自分との関係」がある
経営とは、人との関係の上に成り立つ活動です。
社員・お客様・取引先・家族など、あらゆる人との関係が経営を形づくります。
しかし実は、そのすべての関係性の土台にあるのが「自分自身との関係」です。
自分を信頼できていない経営者は、他人の評価や結果に一喜一憂しやすくなります。
逆に、自分と両想いになっている経営者は、どんな状況でもブレずに判断でき、自然と人から信頼されるようになります。
経営者に多い“自己犠牲型の働き方”
多くの経営者が「みんなのために」「お客様のために」と頑張ります。
もちろんその姿勢自体は尊いものです。
しかし、自分を犠牲にしてまで働くと、いずれ誰のためにもならなくなります。
自分が疲弊すれば、冷静な判断ができなくなり、社員やお客様への配慮も欠けていく。
まさに、善意が悪循環を生む状態です。
自分と両想いになることが、経営の好循環を生む起点
経営とは「自分との対話」の連続です。
自分を知り、受け入れ、信頼できるようになると、他者との関係にも自然と調和が生まれます。
それが、私が提唱する「両想いビジネス」の基本的な考え方です。
では、経営者が自分自身と両想いになることで、どのような変化が起こるのでしょうか?
ここからは3つのメリットに分けてお伝えします。
【メリット1】諸々の人間関係が良好になる
自分との関係が整うと、他者に求めすぎなくなる
人間関係がこじれる最大の原因は、「他人に自分の理想を押しつけること」です。
「もっと頑張ってほしい」「なぜわかってくれないのか」と他者に期待する裏には、自分自身への不満や不安が隠れています。
自分との関係が整うと、そうした過剰な期待やコントロール欲求が消えます。
相手を変えようとせず、相手を尊重できるようになるのです。
すると、不思議なことに、相手もまたこちらを信頼し、協力的になっていきます。
尊重する余裕が生まれると、信頼が積み重なる
経営者が「心の余白」を持つことは、組織全体の空気を変えます。
たとえば、部下がミスをした時、イライラして怒鳴るのではなく、
「大丈夫、どうすれば次に活かせるか考えよう」と言えるだけで、チームの信頼関係は格段に深まります。
経営者の姿勢は、社員にそのまま反映されます。
自分を責めず、他者を責めないリーダーほど、安心感のある組織を育てていくのです。
人間関係の質が経営の質を決める
私はこれまで500件以上の経営支援を行ってきましたが、業績が安定している会社ほど人間関係が良好です。
それは、「経営者が自分と両想い」だからこそ、周囲とも両想いの関係を築けているのです。
人間関係の質こそが、経営の質を決める──それが私の確信です。
【メリット2】成果体質になる
自分を理解すると「得意と好き」に集中できる
経営者は常に多くのタスクに追われています。
しかし、その中で「自分が心から得意で、好きだと感じる仕事」はどれほどあるでしょうか。
自分を理解していないと、不得意な分野にも手を出し、エネルギーを分散してしまいます。
一方で、自分自身と両想いになると、「何を手放し、何に集中すべきか」が明確になります。
「好き」と「得意」に軸を置いた経営ほど、成果の再現性が高まるのです。
本心に沿った行動は、自然と成果を引き寄せる
“努力して頑張る経営”から、“自然体で成果が出る経営”へ。
これは精神論ではありません。
人は「心が納得している行動」をしている時に、最も集中力と創造力を発揮します。
「やらねばならない仕事」よりも「やりたい仕事」にエネルギーを注ぐ。
この小さな選択の積み重ねが、やがて圧倒的な成果を生み出します。
成果体質とは“努力ではなく自然体”で結果が出る状態
両想いビジネスの本質は、無理なく成果が続く「仕組み化」にあります。
自分が心から望む仕事に集中するほど、お客様との関係も良くなり、紹介やリピートが自然に増える。
それが、成果体質の経営者の共通点です。
【メリット3】長時間労働に依存しなくて良くなる
「働いていないと不安」という思い込みを手放す
多くの経営者が、「働かない=怠けている」と感じてしまいます。
しかしそれは、社会の中で植えつけられた“努力信仰”の名残です。
働いていない時間も、経営者にとっては「未来を育てる時間」です。
休むことに罪悪感を持ってしまうのは、自分との関係が希薄だから。
自分を信頼できるようになると、「休むこと=怠け」ではなく、「休むこと=経営」だと理解できるようになります。
あるがままの自分を認めると、焦りが消える
「もっとやらなければ」「まだ足りない」と焦る気持ちは、
自分を信頼できていないサインでもあります。
両想いビジネスの考え方では、「足りない自分を変える」のではなく、「すでにある自分を認める」ことを重視します。
焦りが消えると、判断が冴え、行動の質が高まります。
その結果、短時間でも高い成果を上げられるようになるのです。
「休むことは経営者の責任」という新しい発想
経営者が休める会社こそ、信頼で動く強い組織です。
トップが倒れたら会社も止まる──それは依存構造に過ぎません。
経営者が安心して休める体制を作ることは、社員への最大の信頼の証でもあります。
経営者にとって、最も重要な資産は「自分自身」
どんなに優れたビジネスモデルや戦略を持っていても、
それを動かすのは経営者自身です。
だからこそ、経営者の心の状態こそが、最大の経営資産なのです。
自分を理解し、尊重し、信頼できるようになれば、
人間関係・成果・働き方のすべてが好転します。
それが、両想いビジネスの真髄です。
まとめ|“自分自身と両想い”になることが経営の変革を生む
経営者が自分と両想いになることは、単なる自己啓発ではなく、経営戦略の本質です。
自分を信頼できる人は、他者からも信頼されます。
そして、その信頼の連鎖が、成果と幸福を両立させる経営を生み出すのです。
次の記事では、「自分自身と両想いになる具体的な方法」を解説します。
どのようにして自分との関係を深め、自然体で成果を出せる経営へと変わっていくのか──
その実践ステップを具体的にご紹介します。