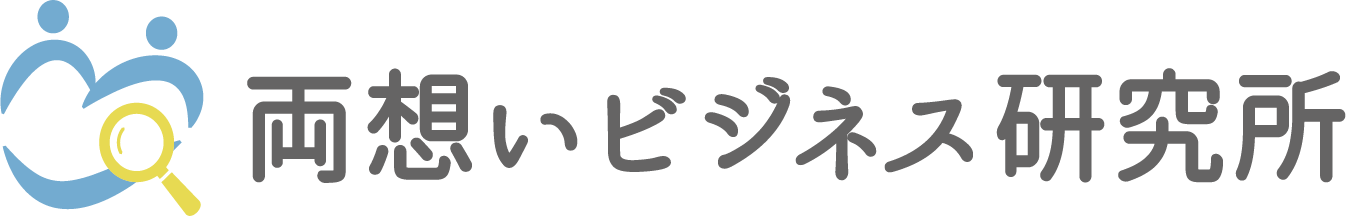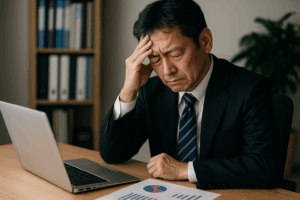働きすぎ経営者の心理を解説|なぜ経営者は休むことに罪悪感を抱くのか?
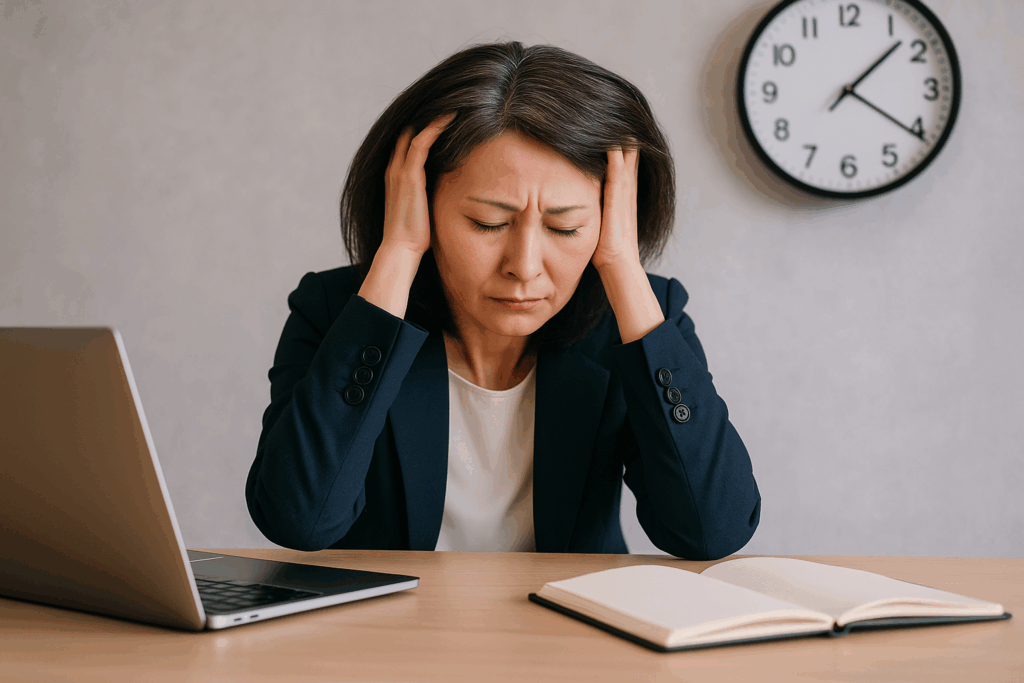
「休みたいけれど、休むと不安になる」──多くの経営者がそんな気持ちを抱えています。
経営者にとって「休むこと」は、心理的なハードルが伴うものです。
本記事では、経営者が休むことに罪悪感を抱く理由を心理学と経営の視点から解説します。
多くの経営者は本心では長時間労働を望んでいない
経営者の労働時間は一般労働者よりも1時間以上長い
働き方改革関連法が施行されて6年。社員の長時間労働を是正しようという動きは社会的に浸透してきました。
一方で、経営者の労働時間はどうでしょうか?
2022年2月の中小企業経営者アンケート調査「大同生命サーベイ」における「経営者の労働実態」によると、経営者の81%が「1日の平均労働時間が8時間以上」と回答しました。
https://www.daido-life.co.jp/knowledge/survey/202202.html
また中小企業庁の公表によると、経営者の1日の実労働時間は全体平均で9時間26分となっており、これは規模が比較的小さい事業所に勤務する一般労働者の平均実労働時間(8時間16分)よりも1時間以上長い労働時間です。
上記から、経営者の多くが長時間労働を行っている実態が浮き彫りになっています。
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/h30/shoukibodeta/html/b2_1_2_1.html
働きすぎ経営者は自らの労働時間に不満を持っている
では、経営者は自らの労働時間について満足しているのでしょうか?
みずほ情報総研株式会社の調査によると、小規模企業経営者の労働時間への満足度は、「大変満足している」「満足している」の合計が30.4%となっています。
一方で、企業勤務者の労働時間への満足度は、「大変満足している」「満足している」の合計が46.4%となっています。
つまり、企業勤務者と比較して、小規模企業経営者の労働時間への満足度は16%も低い数字となっています。
本心では長時間労働を望んでいない経営者が多いことが伺えます。
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/shokibo/b2_3_3.html
なぜ経営者は休むことに罪悪感を抱くのか
強い責任感と「自分がやらねば」の思い込み
経営者は会社の最終責任を負う立場です。
そのため「自分が動かなければ会社が止まる」という思い込みに陥りやすくなります。
責任感は経営に必要不可欠ですが、過剰になると「休むこと=逃げること」という誤った認識を生んでしまいます。
「働いてこそ価値がある」という承認欲求
人間は誰しも承認欲求を持っています。
経営者の場合、社員や取引先から「頑張っている社長」と思われたい気持ちが強く、働き続けることで承認を得ようとします。
この承認欲求が満たされると一時的に安心しますが、やがて「休んだら価値がないのでは」という不安に変わり、休むことに罪悪感を抱くようになります。
仕事中毒が生む“自己有用感”の罠
経営者は「誰かの役に立っている」という自己有用感を強く求めます。
仕事をしている時はその感覚を得やすいため、働くほど満たされますが、休むと一気にその感覚を失い、不安に駆られます。
この心理は「ワーカホリック(仕事中毒)」に近く、やがて長時間労働を常態化させてしまいます。
文化や環境が作る「休めない空気」
日本社会には「長時間労働が美徳」という文化が根強くあります。
「休んでいる=怠けている」という価値観に縛られると、経営者は自ら休むことに罪悪感を覚えるだけでなく、社員にもその空気を押しつけてしまいます。
休むことへの罪悪感が生み出す悪循環
認知資源の枯渇で意思決定を誤る
心理学では、人間が意思決定に使えるエネルギーを「認知資源」と呼びます。
長時間労働で疲弊すると、この認知資源が枯渇し、冷静な判断ができなくなります。
経営における小さな判断ミスが積み重なれば、会社全体を危険にさらすことになります。
社員に「休まないことが美徳」というモデルを植えつける
経営者が休まない姿勢を見せると、社員も「休めない」と感じます。
「社長が働いているのに自分だけ休めない」という空気が蔓延し、結果的に組織全体のモチベーションや生産性を下げる悪循環につながります。
家庭での罪悪感が二重ストレスを生む
「家族と過ごす時間を削ってまで働く自分は良い父親(母親)なのか?」という自責の念を抱える経営者は少なくありません。
仕事中も家庭でも罪悪感に苛まれることで、ストレスは倍増し、精神的にも不安定になります。
パーキンソンの法則──時間は埋め尽くされる
行動心理学で知られる「パーキンソンの法則」によれば、人は与えられた時間をすべて使い切ろうとする傾向があります。
「長時間働く」ことを前提にすると、業務は無限に膨らみ、休む余地はなくなります。
これは経営者にとって最も危険な落とし穴です。
心理学から見る罪悪感の正体
罪悪感は「認知の歪み」から生まれる
心理学的に見ると、経営者が休むことに罪悪感を覚えるのは「認知の歪み」の一種です。
「休む=悪いこと」という極端な思考パターンが、根拠のない不安を作り出しています。
過去の成功体験が“休めない習慣”を強化する
「頑張って成果を出した」という経験は成功体験として記憶されます。
しかし、それが「休まず働けば成果が出る」という誤った方程式を強化し、休むことへの抵抗をさらに強めてしまいます。
マズローの「自己実現欲求」がゆがんだ形で表れる
マズローの理論の最上位には「自己実現欲求」があります。
本来は自分の可能性を最大限に発揮するための欲求ですが、働きすぎ経営者の場合「働き続けなければ実現できない」という誤った形で表れ、結果的に自分を追い込んでしまいます。
承認欲求よりも「自己受容」が経営者を救う
承認欲求に依存している限り、休むことは常に罪悪感を伴います。
しかし「休んでも自分には価値がある」と自己受容できるようになると、経営は格段に安定します。
自己受容は、長期的に成果と幸せを両立する経営者に不可欠な基盤です。
まとめ|罪悪感を手放せば経営はもっと豊かになる
経営者が休むことに罪悪感を抱く理由は、責任感や文化だけでなく、心理学的な「承認欲求」「自己有用感」「認知の歪み」にもあります。
しかし、それらは根拠のある必然ではなく、思い込みや習慣にすぎません。
罪悪感を手放すことで、経営判断は研ぎ澄まされ、社員や家族との関係も良好になり、経営はもっと豊かに持続可能なものへと変わっていきます。
次の記事では「経営者が休むと社員・お客様・家族が幸せになる理由」について解説します。