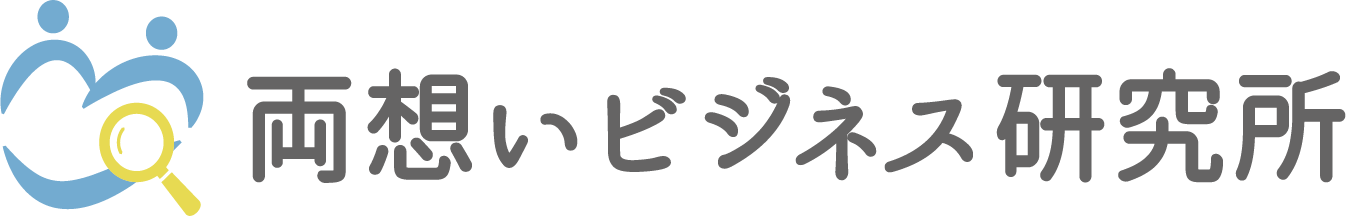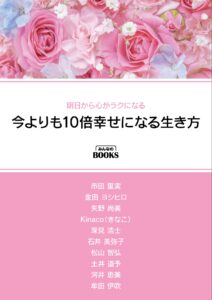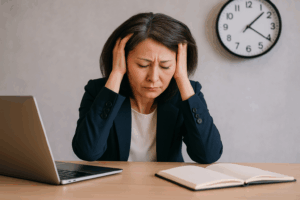働きすぎ社長の落とし穴|経営者の長時間労働が招く悪循環
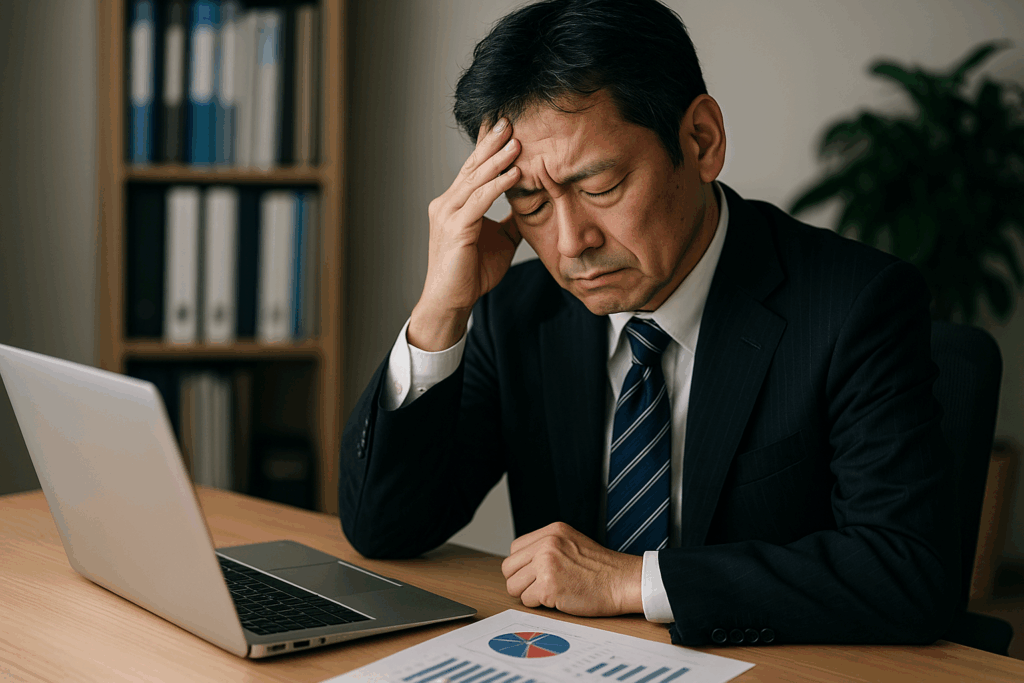
「社長が誰よりも働くのは当たり前」「自分が頑張らなければ会社は回らない」――多くの経営者がそう信じています。
しかし実際には、経営者の長時間労働は成果を生むどころか、会社に深刻な悪影響を及ぼすことが少なくありません。
この記事では、経営者の長時間労働がもたらす“悪循環”について整理し、なぜ働きすぎが経営を弱体化させてしまうのかを解説します。
なぜ経営者は長時間労働に陥りやすいのか
経営者特有の強い責任感と孤独
経営者は常に「最終責任を負う立場」にあります。
社員や取引先、顧客、さらには家族の生活を背負っているという感覚から、「自分が頑張らなければ」という意識に陥りがちです。
さらに、悩みを打ち明けられる相手が少なく、孤独を抱えたまま仕事にのめり込んでしまうことも、長時間労働に拍車をかけています。
「自分がやらなければ会社が回らない」という思い込み
「社長がやらないと品質が落ちる」「社員にはまだ任せられない」といった思い込みが、経営者を休めなくさせています。
結果的に細部まで社長が抱え込み、戦略的な仕事に集中できず、労働時間だけが膨れ上がっていきます。
成果を出すほど休めなくなる“成功の罠”
業績が上がるほど、経営者は「もっと成果を出さなければ」と考えがちです。
この心理は一見ポジティブに見えますが、次第に休むことへの罪悪感や焦りを生み、さらに働きすぎるという悪循環に陥ります。
経営者の長時間労働が招く3つの悪循環
意思決定の質が低下する
疲労やストレスが蓄積すると、視野が狭くなり、冷静な判断ができなくなります。
小さな判断ミスが積み重なることで、会社全体の方向性を誤るリスクが高まります。
経営は“質の高い意思決定の連続”である以上、疲弊した状態での長時間労働はむしろ経営を危険にさらします。
社員の士気と生産性が下がる
「社長が休まないのだから、自分たちも休めない」――そんな空気が職場に広がります。
社員はモチベーションを失い、質の高い仕事ができなくなり、離職の原因にもなります。
経営者が率先して長時間労働を続けることは、会社全体に“休めない文化”を根づかせる危険性をはらんでいます。
お客様や家族との関係が悪化する
働きすぎは、お客様や家族との関係にも影を落とします。
疲れた状態では顧客への対応が雑になりやすく、信頼を失うことも少なくありません。
また、家族と過ごす時間が減れば、経営者自身の心の支えを失い、仕事への集中力も低下してしまいます。
働きすぎ社長が抱える「隠れコスト」
健康を損ない、医療費・欠勤リスクが増大
長時間労働は心身をむしばみ、体調不良のリスクを高めます。
体調を崩して入院すれば、直接的な医療費だけでなく、会社の舵取りができないという大きな損失につながります。
私自身も、働きすぎが原因で「高熱が数ヶ月続く」という体調不良になり、顧客がゼロになる苦い体験をしたことがあります。
離職率や人材流出につながる“社内コスト”
社長が働きすぎている会社ほど、社員も疲弊しやすく、優秀な人材ほど離れていきます。
採用・教育にかかるコストは膨大であり、人手不足の時代における人材流出は会社の成長を阻害する大きなリスクです。
長期的な成長を阻害する“見えない赤字”
経営者が日々の業務に追われすぎると、中長期的な戦略立案がおろそかになります。
その結果、新しいチャレンジやイノベーションが生まれず、気づけば市場で取り残されてしまうリスクがあります。
これこそが、数字に表れない“見えない赤字”と言えます。
まとめ|働きすぎは経営を弱体化させる
経営者の働きすぎは、美徳でも責任感の証でもありません。
むしろ、意思決定の質低下・社員のモチベーション低下と人材流出・お客様や家族との関係悪化といった悪循環を生み出し、会社を弱体化させる原因となります。
今こそ「経営者自身の働き方改革」を目指してみませんか?
次の記事では「なぜ経営者は休むことに罪悪感を抱くのか」について解説します。