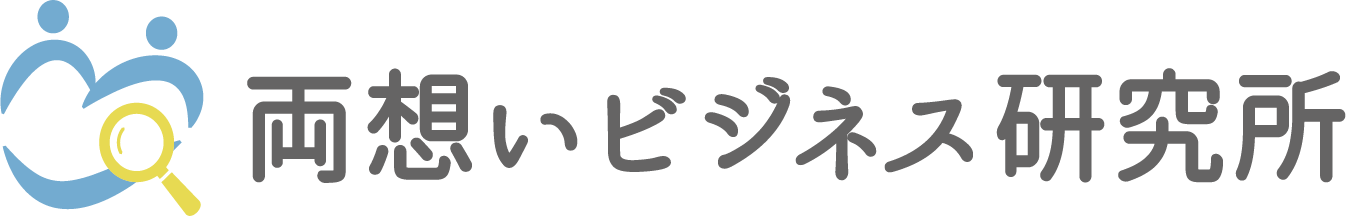【経営者必見】S.RIDEが月10回以上使われる理由 ─ GO・DiDiに勝る“3つのリピーター戦略”とは?

はじめに ─ タクシーアプリ市場に見る「リピート獲得」の本質
競争激化するモビリティ業界で勝ち続けるには?
タクシーアプリ市場は今、激動の渦中にあります。「GO」や「DiDi」、さらには世界的なプラットフォーム「Uber」まで、各社が熾烈なシェア争いを繰り広げる中で、異彩を放つ存在がS.RIDE(エスライド)です。派手な広告や大規模キャンペーンではなく、“使われ続ける設計”を武器に、月10回以上使うヘビーユーザーを数多く抱えるこのアプリは、まさにリピーター獲得戦略の優等生といえるでしょう。
競合が全国展開や価格競争に注力する中、S.RIDEは都市部に特化し、ユーザーの行動導線に密着したアプローチで高い定着率を誇っています。本記事では、その秘密に迫ります。
本記事の目的:S.RIDEから学ぶ“顧客を習慣化させる”戦略
マーケティングの世界では、新規顧客の獲得だけでなく、「リピーターの創出」も重視されています。その理由は明確です。リピーターはLTV(顧客生涯価値)を高め、広告費や人件費といったコストの回収期間を短縮し、事業の安定性を高めるからです。
S.RIDEは、まさにその“リピーター創出”を重視したビジネスモデルを採用し、他のタクシーアプリとは異なる道を進んでいます。本稿では以下の点を明らかにしながら、どの業種でも応用可能な「リピーター戦略の本質」を掘り下げていきます。
- なぜS.RIDEは月10回以上使われるのか?
- 競合と何が違うのか?
- どんな設計思想やマーケティング施策がユーザーを惹きつけているのか?
- それは他のビジネスにどう応用できるのか?
「顧客を“満足”ではなく“習慣”にする」──この視点こそ、今後のサービス設計・事業戦略において不可欠なカギとなります。S.RIDEの事例を通じて、そのヒントを紐解いていきましょう。
タクシーアプリ市場の今──なぜリピーターが鍵になるのか?
GO・DiDi・Uber Japan…プレイヤー乱立の実態
近年、タクシー配車アプリ市場には国内外の大手企業が相次いで参入し、まさに“戦国時代”の様相を呈しています。業界最大手「GO」は、日本交通ホールディングスとディー・エヌ・エー(DeNA)が筆頭株主のプラットフォームで、現在は全国47都道府県への展開を目指し急拡大中です。
一方、中国発の「DiDi」や米国発「Uber Japan」も、割引プロモーションや外国人観光客向けのインバウンド需要を武器に利用者を拡大し続けています。
しかし、こうした市場拡大の裏で、ユーザーの“アプリ使い分け”と“離脱”が加速しているのも事実です。アプリをインストールしても1回使ったきりで終わるケース、またクーポンが使えなくなった途端に離脱するユーザーも多く、各社が継続利用に課題を抱えているのが現状です。
利用頻度で収益が決まる「LTV主導型モデル」の構造
この業界における最大の収益源は、タクシー利用者の1回あたりの手数料(マッチングフィー)です。つまり、アプリを1回使ってもらうだけでは収益化に時間がかかり、いかに「継続的に使ってもらえるか」が重要になります。
そのため、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を最大化する戦略が各社で重視されています。LTVを押し上げるには、以下の要素が重要です:
- ユーザーの利用頻度(F:Frequency)
- 継続期間(T:Time)
- 顧客満足度と定着度(Retention)
S.RIDEが注力しているのは、この「頻度」と「定着」に強く働きかける設計です。派手なマーケティングではなく、ユーザーの毎日に自然に組み込まれるようなUXと戦略を徹底しているのが特徴です。
一見派手なキャンペーンがリピートにつながらない理由
競合アプリがしばしば打ち出す「初回限定1,000円割引」や「友達紹介でポイント進呈」といった施策は、確かに短期的な新規流入には効果的です。しかし、こうしたキャンペーン施策に依存しすぎると、ユーザーは“得する間だけ”使って離れてしまう傾向があります。
さらに、価格以外で差別化しにくい市場では、プロモーション競争が激化し、ユーザーのロイヤルティが育たないという弊害も生まれています。タクシーという日常的なサービスにおいて、「安いから使う」ではなく「便利だから、いつもこれ」という定着状態が理想です。
その理想に、最も近い成果を上げているのがS.RIDE。では、なぜS.RIDEだけが「使われ続ける」存在になれたのか?
次章では、サービスの設計思想やビジネスモデルを紐解きながら、その答えを探っていきます。
S.RIDEとは何か──サービスの全体像と事業戦略
ソニー×タクシー=S.RIDEの立ち位置
S.RIDE(エスライド)は、ソニーグループが提供するタクシー配車アプリです。2019年にサービスを開始し、現在は東京を中心に1都3県(埼玉・千葉・神奈川)に加え、関西や中部地方など、首都圏を含む9都府県で展開しています。
S.RIDEの最大の特徴は、ソニーの技術力を活かしたUI・UXのシンプルさと、地元のタクシー会社との緊密な提携関係です。派手なテレビCMや全国展開を狙うのではなく、“地域密着型かつ高頻度利用者に愛される設計”に注力している点が、他社との明確な違いです。
一見ニッチに見えるこの戦略が、実はマーケティング視点からは非常に合理的であり、LTV最大化に直結しています。
提供エリア・提携タクシー会社・利用者層(30代中心)などの特徴
S.RIDEは、全国展開よりも都市部の生活導線に深く入り込む「都市集中戦略」を選択しています。多くのタクシー会社と提携し、2万台以上の配車ネットワークを構築。都市部での利便性は他社に引けを取りません。
利用者の中心は、30代のビジネスパーソン。通勤や出張、外回りの営業、会食などのシーンで高頻度に利用される傾向があります。また、S.RIDE株式会社の公式発表によると、2024年7月にS.RIDEによる乗車回数が過去最高となる月間100万回を突破し、約半数近くが月に10回以上利用しているユーザーによる配車だったとのことです。
https://www.sride.jp/jp/list/20240807/
特筆すべきは、このユーザー層が価格よりも“確実に配車できること・使いやすさ”を重視している点です。つまり、一度「これが便利だ」と実感すれば、他アプリに浮気せずに使い続ける傾向があるのです。
高リピート率(月10回以上)の裏にある設計思想
S.RIDEの高いリピート率を支えているのは、偶発的なヒットではなく、意図的に設計された3つの戦略的柱です。それが次章以降で詳しく解説する以下のポイントです:
- 都市特化型ポジショニング
特定エリアに絞ってユーザー導線に入り込み、生活の一部として定着させる。 - 摩擦ゼロのUX設計
誰でも直感的に使えるUI、シンプルな画面遷移、ワンタップで配車が完了する“迷わなさ”の設計。 - 習慣化マーケティング
プッシュ通知やタイミング設計でユーザーの“日常行動に寄り添う”体験を生み出す。
これらはどれも、マーケティングの世界で語られる「リテンション戦略」「LTV最大化」「行動経済学的アプローチ」といった視点とも一致します。つまり、S.RIDEは偶然リピートされているのではなく、“リピートされるように作られている”のです。
次章では、この設計の中核とも言える「戦略①:都市特化型ポジショニング」について詳しく見ていきましょう。
戦略①:エリアを絞り「日常導線」に入り込む“都市特化型ポジショニング”
なぜ全国展開しないのか?──「選択と集中」の意思決定
S.RIDEの最大の特徴は、“あえて全国展開を急がない”戦略にあります。競合他社が全国47都道府県への対応を進める中、S.RIDEはサービス提供エリアを9都府県に限定しています。これは、単にリソースの制約ではなく、明確な戦略的意思決定「選択と集中」に基づくものです。
配車アプリの性質上、ユーザーは「今すぐ」「この場所で」タクシーに乗れることを期待します。つまり、エリアごとの供給密度(台数)と対応品質が非常に重要なのです。全国に拡散するよりも、特定地域で“使えば必ず来る”という信頼感を作るほうが、LTVを高めるには効果的です。
結果として、都心部では「GOより早く配車できた」「DiDiより安心して使える」といったユーザー評価が蓄積され、高頻度ユーザーの獲得と定着につながっています。
ターゲットは誰か?──30代ビジネスパーソンの生活圏に刺さる設計
S.RIDEが最も重視するのは、「誰に使ってもらうのか」というターゲット設計です。注力しているのは、30代〜40代の都市部で働くビジネスパーソン。この層は、以下のような行動特性を持っています:
- 毎日決まった時間に通勤・移動する
- タクシーのコストより時間効率を優先する
- アプリでのUXや操作性に敏感
S.RIDEは、これらのニーズに応えるため、一瞬で配車できるUX、対応台数の多さ、都心部での走行実績の多さを揃えることで、競合よりも「便利で頼れる存在」として記憶に残る設計にしています。
これにより、ユーザーの中に「移動=S.RIDE」という無意識の選択が刷り込まれ、結果的にリピート率を押し上げているのです。
地方展開との比較と、都心戦略の成功要因分析
では、なぜ地方展開では同じ戦略が難しいのか。理由は以下の通りです:
- 地方ではタクシーの稼働台数が少なく、即時配車が困難
- 日常の移動が自家用車中心で、そもそも利用頻度が低い
- ユーザーがタクシーアプリに求める期待値が都市部とは異なる
このように、地方市場は「リピーター戦略」に不向きであり、S.RIDEのビジネスモデルとは相性が悪いことが分かります。
逆に言えば、S.RIDEはこの制約を理解し、「都市で戦うからこそ、勝てる」設計を徹底しています。これはリソースが限られた中小企業にとっても重要なヒントで、無理に広げず、強みを発揮できる場所で勝つという戦略の本質を示していると言えるでしょう。
戦略②:アプリUXの最適化がリピート行動を生む──「迷わず使える」の価値
ワンタップ配車に込められた“摩擦ゼロ”設計
S.RIDEのアプリを立ち上げると、まず驚くのがその圧倒的なシンプルさです。現在地を自動で認識し、行き先を入力せずともワンタップで配車が可能。これは「S.RIDE(エスライド)」というネーミング自体が示す通り、“スムーズに乗る”ことを究極まで突き詰めた設計思想の結果です。
一般的な配車アプリでは、以下のような操作が必要です:
- 行き先の入力
- 車種やオプションの選択
- クーポンの適用
- 配車ボタンを押す
しかし、S.RIDEではこれらのステップを徹底的に簡略化し、初回以降は基本的に1〜2アクションで配車完了。UXデザインにおける「認知的摩擦(Cognitive Friction)」を極限まで取り除いたこの構造は、「考えずに使える=毎日使える」というユーザー習慣につながります。
UI・機能・画面遷移のシンプルさがもたらす“心理的定着”
マーケティング心理学においては、「選択肢が多いほどユーザーは動かない」と言われます。これは“選択のパラドックス”と呼ばれ、特に毎日使うツールやアプリにおいては「迷わず、すぐに使える」ことが最大の価値になります。
S.RIDEはこの原則に忠実です:
- メニュー構成は極限までシンプルに
- 配車までの画面遷移は最短
- クーポンや通知も“邪魔にならない設計”
この設計によって、ユーザーは「何も考えずにタクシーを呼べる」体験を得ます。結果として、使うたびに“便利だった”という成功体験が積み重なり、他アプリへの乗り換えコストが心理的に高まっていくのです。
UXがLTVを左右する:SaaSやECにも通じる原則
この「UX=LTV」という考え方は、実はSaaS業界やEC業界でも定番のセオリーです。例えば:
- サブスク型SaaS:操作が難しいと、契約してもすぐ解約される
- ECサイト:購入までの導線が長いと、カゴ落ち率が上がる
タクシーアプリも同じで、1回目の利用体験がスムーズでないと、2回目は来ません。S.RIDEのように「使ってストレスゼロ」を実現することが、リピーター獲得には不可欠です。
これは、飲食店・美容院・医療機関・習い事など、あらゆる業種のデジタル施策にも通じる原則です。ユーザーが「またここで頼もう」「次も使いたい」と思うのは、情報量や割引ではなく、「使いやすさ」「わかりやすさ」「めんどくさくなさ」なのです。
戦略③:日常に溶け込む「習慣化マーケティング」
毎日の通勤・通院・買い物に“自然に入り込む”仕組み
S.RIDEの成功は、単にアプリが使いやすいという技術的な優位性だけではありません。その真価は、ユーザーの日常生活に自然に入り込む設計にあります。
たとえば、毎朝の通勤時にタクシーを使うビジネスパーソンにとって、「駅まで5分早く着ける」「雨の日に濡れずに移動できる」といった“体験価値”が蓄積されると、「また使おう」「今日もS.RIDEでいいや」という心理が生まれます。
ここで重要なのは、S.RIDEがこの行動パターンを習慣化させるための導線を細かく整備している点です。人は「一度でも便利だった」と感じると、次回もその選択を繰り返す傾向があります(これを“初回体験の定着化”と呼びます)。S.RIDEはその初回の成功体験を、日常の中に違和感なく溶け込ませる設計をしています。
プッシュ通知/アプリ内イベント/限定クーポンの出し方
ユーザーとの接点を増やすために、S.RIDEは以下のような習慣化マーケティングの手法を活用しています。
- プッシュ通知:通勤時間帯や悪天候時など、ユーザーが“使いたくなる”タイミングにあわせて配信。
- アプリ内イベント:「5回乗車で1回分無料」など、ゲーミフィケーション要素を取り入れた企画。
- 限定クーポン:場所や時間帯を限定することで、行動を“促すきっかけ”として活用。
これらは単なる販促手法ではありません。重要なのは、「使う理由を与える」という点です。タクシーを使わないと損だと感じさせたり、乗れば得するという状況を自然に作り出すことで、ユーザーの行動頻度を高め、“繰り返し使いたくなる仕掛け”になっているのです。
繰り返し使いたくなる仕掛け:「選択疲れ」の回避と期待感の設計
現代人は、日々膨大な選択を強いられています。特にスマホの中には無数のアプリが並び、どれを使うかという判断すら疲労を招くこともあります。この「選択疲れ」に対する最適なアプローチこそ、“迷わず使える”“他と比べずに使える”状態の構築です。
S.RIDEでは、「アプリを開いたらすぐ配車できる」という予測可能な体験を提供することで、ユーザーに安心感と習慣化を促します。さらに、頻度が上がるごとにクーポンがもらえたり、イベントに招待される仕組みも用意されており、“次に使いたくなる期待感”を常に維持しています。
このように、「行動のトリガー→快適な体験→次回への期待」という好循環を作り出すことで、S.RIDEはユーザーを“習慣的なヘビーユーザー”へと育てているのです。
競合との比較で見えてくるS.RIDEの“際立った違い”
GOの「全国展開」との差別化ポイント
日本最大手のタクシー配車アプリ「GO」は、その名の通り、全国規模でのサービス提供を志向しています。大手タクシー会社との連携を活かし、都市部から地方まで幅広く対応することが特長です。しかし、この“網羅性”は裏を返せば、エリアごとのサービス最適化が難しいという課題にもつながります。
一方、S.RIDEは戦略的に首都圏を中心とした“都市特化型”の展開に絞っています。これはリソースを一点集中する「選択と集中」の好例であり、地域のニーズにより深く応えるUXやプロモーションが実現可能になります。
特に、30代〜40代の都市生活者に向けた「移動のルーチン」に入り込む設計(例:朝の通勤、終電後の移動など)は、全国的なカバーを優先するGOでは実現しにくい、“エリア密着型の強さ”だと言えるでしょう。
DiDiやUberの「割引依存モデル」との違い
一方、DiDiやUberといった外資系アプリは、参入初期から大規模な割引キャンペーンを武器にユーザー数を伸ばしてきました。たとえば「初回1,000円割引」「10回まで半額」といったインセンティブ施策は、ユーザー獲得には有効ですが、定着につながらないという副作用も抱えています。
ユーザーの多くが“割引ありき”の利用動機である場合、キャンペーン終了とともに離脱するリスクが非常に高いのです。
S.RIDEはこの点で一線を画します。派手なクーポンではなく、“毎回の使いやすさ”“日常に溶け込む快適さ”という本質的価値でリピートを促す設計になっているため、利用頻度が極めて高く、月10回以上のユーザーも珍しくありません。
これは短期的なユーザー数の増加ではなく、中長期的なLTVの最大化を重視した戦略の結果であり、マーケティング視点でも極めて合理的です。
単なる機能比較ではなく“戦略の芯”に違いがある
配車アプリというと、「アプリの見た目」「料金」「車両の数」といった表面的な比較に終始しがちですが、S.RIDEの強さはそこにはありません。
重要なのは、どのようなユーザーに、どのような体験を提供し、なぜ繰り返し使われるのかという“戦略の芯”が明確であることです。
- GO:全国網羅型によるブランドスケール戦略
- DiDi/Uber:割引キャンペーンによる短期利用者拡大戦略
- S.RIDE:都市特化・UX最適化による“習慣化”リピーター戦略
この違いは、単なる配車サービスの話に留まりません。どのビジネスにおいても「誰を顧客とし、どう定着させるか」を考える上での示唆に満ちています。
S.RIDEから学べる、全業種に通用する「リピーター戦略」の原則
顧客が“選ぶ”のではなく“戻ってくる”ために必要な3つの条件
S.RIDEの戦略は、単なる「便利なアプリ」の話ではありません。これは、業種を問わず“顧客が定着するビジネスモデル”の構築法として、他業界にも応用可能です。では、顧客が“毎回選び直す”のではなく、“当然のように戻ってくる”状態を作るには何が必要なのでしょうか。
以下の3つが、その鍵を握ります。
- 摩擦のない体験設計
選ぶ・使う・終えるまでの一連の行動にストレスがない。UXの最適化、導線の整理、UIの明快さなど、「考えずに済む」仕組みを徹底する。 - 日常行動への自然な統合
特別なイベントでなくても、いつもの生活の中で使えること。これは顧客の“日常導線”を理解し、そこに製品やサービスを“寄り添わせる”設計が必要です。 - 小さな期待感を持続させる工夫
「また使いたい」と思わせるような、次回のメリットや新鮮さの提供。限定情報、リワード、顧客体験の向上などで、継続利用を“感情的に支える仕組み”を整えることがポイントです。
S.RIDEはこの3つを高水準で満たしているからこそ、「毎月10回以上」使うヘビーユーザーを多く抱えるに至っているのです。
中小企業・ローカルビジネスでも使えるヒント
「それはS.RIDEみたいな大企業だからできるんでしょ」と思われるかもしれません。しかし、戦略の本質はスケールに関係なく応用できる要素です。
たとえば、地方の飲食店が顧客のリピート率を上げたいなら:
- UXの最適化:モバイル注文・予約システムの導入で、ストレスなく注文できる体験に。
- 生活導線への統合:通勤路や子供の送り迎え動線に合わせた営業時間・メニュー設計。
- 期待感の持続:来店回数に応じた特典、月替わり限定メニューなど、小さなサプライズを織り込む。
つまり、重要なのは規模ではなく、「誰にとって、どう心地よいか」を徹底的に考え抜く姿勢です。これが、リピート行動を生む“ビジネス設計力”につながります。
「まずはここから」:明日から真似できる行動チェックリスト
以下は、S.RIDEの戦略から抽出した、すぐにでも着手できる“リピーター戦略の第一歩”です。
- □ 顧客が毎回迷わず使えるような、わかりやすい導線や手順になっているか?
- □ 顧客の生活リズムや行動パターンに、商品・サービスが自然に組み込まれているか?
- □ 利用後、次回への期待を作るような要素(特典・通知・提案)があるか?
- □ 割引ではなく、「また使いたくなる理由」をきちんと設計できているか?
- □ “たまたまの選択”から“当然の選択”へ──この変化をどう起こすかを考えているか?
これらは、S.RIDEのようなタクシーアプリに限らず、あらゆる業種で活かせる考え方です。小さな一歩の積み重ねが、“選ばれるブランド”から“戻ってこられるブランド”への進化を生み出します。
おわりに ─「使われ続けるサービス」はどう作るか?
“高頻度ユーザー”という資産を持つことの強さ
S.RIDEの成功は、派手な広告でも、革新的な技術でもありません。最大の武器は、「高頻度で使ってくれるユーザー=“習慣化された顧客”」を獲得・維持している点にあります。
月10回以上という利用頻度は、単なる便利さだけでは到達できません。サービスが生活の一部として機能している証拠であり、そこには「UX」「マーケティング」「顧客理解」すべてが連動した設計があります。
このような“高頻度ユーザー”は、いわば企業にとっての「無形資産」です。彼らの存在が、以下のような多くの恩恵をもたらします。
- LTV(顧客生涯価値)の向上
- 安定的な売上の土台
- ポジティブなクチコミや紹介による新規顧客獲得
- プライシングや機能変更への柔軟な対応力
つまり、広告に頼らなくても“使われ続ける力”こそが、サステナブルなビジネスの鍵なのです。
顧客定着こそが、事業の持続可能性を決める
S.RIDEが証明しているように、リピーター戦略の設計こそが、競争の激しい市場での「生き残り戦略」です。
特に、あらゆる業種・業界で「モノやサービスの差別化」が困難になっている今、顧客との“関係性”に目を向けることが、最大の差別化となります。
目指すべきは、選ばれることより、“戻ってきてもらえる”状態。
それは、「サービスの完成度」と「人間の心理」を深く理解し、丁寧に接点を設計することでのみ実現します。華やかな打ち上げ花火よりも、静かに灯り続けるランプのような価値提供が、ブランドとしての信頼と継続性を支えるのです。
最後に
「リピーターは売上の8割を生む」とも言われる時代において、S.RIDEの戦略は、まさに現代的な“顧客戦略”の教科書といえる存在です。
もしあなたが、サービス業、店舗経営、サブスクリプション、オンライン事業、どんな業界にいても、今日からこう自問してみてください。
「うちの顧客は、なぜもう一度使ってくれるのだろうか?」
「その理由を、どうやって設計しているだろうか?」
答えが明確でないなら、S.RIDEが提示してくれたヒントを、ぜひ明日からの経営に役立ててみてください。リピーターこそ、企業の未来を支える最強のマーケティング資産です。