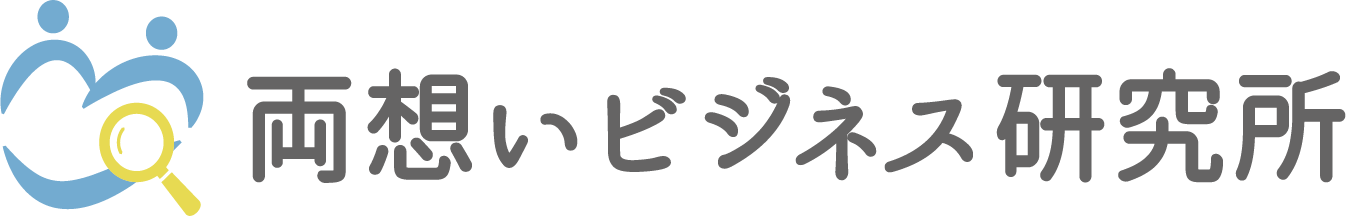電動キックボード「LUUP」失敗の現実|経営者が見落とした“現場の声”が命取りに?

コロナ禍を背景に「密を避けたスマートな移動手段」として注目を集めた電動キックボード。その代表格ともいえるシェアサービス「LUUP」は、都市部を中心に急速に広がりを見せました。
しかし今、全国の自治体でLUUPのポート撤去が進み、社会から静かに姿を消しつつあります。放置・事故・歩行者とのトラブル──パリでは住民投票の末に全面禁止となり、日本でも同じ道をたどる兆しが見えています。
なぜ、便利なはずのサービスがここまで急速に失速したのか?
本記事では、LUUPの事例をもとに、経営者が見落としがちな“現場の声”の重要性を掘り下げ、ビジネスに活かすべき教訓を紐解きます。
LUUPとは何だったのか?〜電動キックボードブームの背景〜
都市交通を変える“スマートモビリティ”として注目
LUUPは、都市の移動をより効率的にすることを目的としたシェア型電動キックボードサービスです。
「ポート」と呼ばれる専用の乗り捨てポイントを街中に配置し、スマホ一つで誰でも簡単に利用できる利便性は、通勤や観光、ちょっとした移動に革命をもたらすと期待されていました。
日本では、2020年以降に本格展開を開始。電動モビリティの規制緩和と社会的関心の高まりを追い風に、都市部を中心に急速に拡大しました。
パリ発の成功モデルを日本に持ち込んだLUUPの戦略
LUUPのビジネスモデルは、フランス・パリを中心にヨーロッパで成功していたシェア型キックボードに着想を得たものでした。
欧州ではすでに数十社が参入し、都市交通の新たな選択肢として市民権を得ていたことから、日本でも同様のニーズがあると判断されたのです。
実際、初期段階では一定の利用者から好意的に受け入れられ、メディア露出も多く、スタートアップの成功例として取り上げられていました。
なぜLUUPは日本で失速したのか?
撤去ラッシュが示す「歓迎されない便利さ」
2024年以降、都内をはじめとした各自治体でLUUPポートの“撤去”が静かに進行し始めます。
一見すると、行政や市民との摩擦が原因に見えますが、根本には「歓迎されていなかった利便性」があります。
確かに、ユーザーにとっては便利だったかもしれません。しかし、利用者以外の住民にとっては、歩道を占拠するポートや、無造作に置かれたキックボードは迷惑以外の何ものでもありませんでした。
想定以上に多かった放置・事故・苦情
LUUPの公式サイトによると、安全教育の徹底やGPSによる管理体制が整備されていたとされています。
しかし実際には、歩道上での放置、自転車道での危険運転、歩行者との接触などが相次ぎ、SNS上では「危ない」「邪魔」といった声が日常的に見られるようになりました。
自治体や管理者への苦情も増え、地域住民の反対が表面化。都市の中で“共存”できるサービスではなかったことが、次第に明らかになっていきました。
パリでの“全面禁止”は対岸の火事ではなかった
LUUPが参考にしたフランス・パリでは、2023年4月に住民投票が実施され、実に89%が「全面禁止」に賛成。
その結果、同年9月にはレンタル電動キックボードが市内から完全に姿を消しました。
この結果は、単なる「交通マナーの違い」では説明できません。社会が「このサービスはいらない」と明確に判断した例であり、日本においても同様の現象が起こりつつあるのです。
「現場の声」をどう捉えるかが、事業の明暗を分ける
「使いにくい」「怖い」「邪魔」…誰の声を拾っていたのか?
LUUPが最も見落としていたのは、「現場のリアルな声」かもしれません。
ユーザーは“便利”と感じたかもしれませんが、非ユーザー──つまり街の多くの住民にとっては“迷惑”でした。
「自分たちはきちんとルールを守っている」と考えていたとしても、それが社会にどう受け止められているかは別の話です。
企業が独自に収集したデータだけで判断し、ネガティブな反応を軽視した結果、LUUPは“歓迎されない存在”になってしまったのです。
アンチの声=貴重な改善チャンスと捉える視点
経営者はしばしば「批判的な声」を無視したくなります。
しかし、真の意味でプロダクトやサービスを磨くには、批判に対して感じたことを通じて自社を知る必要もあります。
もしLUUPが、早い段階で地域住民や非ユーザーの声に耳を傾け、共存できるインフラ設計へと舵を切っていれば、撤去という事態には至らなかったかもしれません。
LUUPの失敗から学ぶ、経営者が見直すべき3つの視点
① 顧客視点の“価値”がサービス設計に反映されているか?
LUUPは「都市交通の課題を解決する」と掲げましたが、実際には“都市の不便”を増やす存在として認識されるようになってしまいました。
本当にユーザーが「価値がある」と感じる部分と、社会が「許容できる」バランスを取れていたかを再検証すべきです。
② 社会インフラとしての責任を果たしているか?
LUUPのようなシェアモビリティは、社会インフラの一部として機能するものです。
インフラとしての責任(安全性・景観・住民との共存)を果たす設計思想が欠けていたことが、サービス持続性の欠如につながりました。
③ 外国の成功事例をそのまま模倣していないか?
パリの成功をそのまま日本に持ち込む。これは一見合理的ですが、文化・法制度・街の構造・国民性が異なる中で、成功するとは限りません。
模倣よりも「なぜそのモデルが成立したか?」を深く分析し、日本市場での最適解を探すことが求められます。
まとめ:LUUPは他人事ではない。“現場の声”を経営に活かすには
LUUPの事例は、単なる一企業の失敗にとどまりません。
顧客や社会の声にどう向き合うかは、すべての事業者にとっての課題です。
「使いやすい」「便利」だけでは、サービスは長続きしません。
社会に受け入れられ、継続的に使われるためには、「現場の声」に耳を傾け、それを経営に反映させる柔軟さが不可欠です。
いま一度、自社のサービスや商品が「本当に必要とされているか」「誰の声を拾っているか」を問い直してみてはいかがでしょうか。