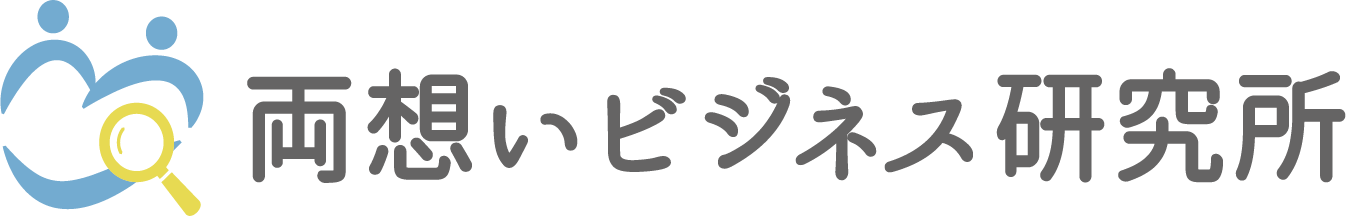話題性だけでは生き残れない|コールド・ストーン衰退から読み解く顧客維持とマーケティング戦略

なぜコールド・ストーンは“話題止まり”で終わったのか?
2005年、アメリカから日本に上陸した「コールド・ストーン・クリーマリー」。注文を受けてからアイスクリームを冷たい石板の上で練り合わせるライブ感、そして店員が笑顔で歌を披露するというエンタメ性あふれる接客で、一気に話題となりました。
最盛期には全国に34店舗を展開。しかし現在は、4月28日に原宿店が、5月6日に佐野プレミアム・アウトレット店が閉店し、三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島店の1店舗を残すのみとなりました。なぜ、ここまで急激に衰退したのでしょうか? 本記事ではその理由を分析し、話題性に頼らず顧客を惹きつけ続けるためのマーケティング戦略について考察します。
なお、アメリカ本国では1600店舗以上を展開する成功ブランドであり、日本での失敗はそのままビジネスモデルの欠陥とは言い切れません。では、何が日本市場での定着を阻んだのでしょうか? あなたのビジネスは“話題性”で終わっていませんか?
コールド・ストーンはなぜ衰退したのか?
かつての人気と急成長の背景
コールド・ストーンの日本上陸は、当時のスイーツ市場に一石を投じました。ライブ感のあるパフォーマンス、トッピングの自由度、そして何より“歌う店員”という非日常体験が、多くの若年層の心を掴みました。
SNSの黎明期にもかかわらず、メディアや口コミで「楽しい」「インスタ映えする」と注目され、一種の“行列ができる体験型ショップ”としてブームに火がつきました。ブランド体験が新鮮で、1度は訪れたくなる店舗だったのです。
また、当時のスイーツトレンドを振り返ると、パンケーキやクレープなど、見た目の華やかさが支持される時代でした。その中で、冷たい石の上でミックスされるカラフルなアイスクリームは、ビジュアル・味・演出の三拍子が揃った“話題になるスイーツ”として、若年層—特に10〜20代の女性を中心に人気を博しました。テレビや女性誌でも取り上げられ、一気にブランド認知を獲得しました。
衰退の兆しと店舗数の減少
しかしその話題性は長く続きませんでした。初回は楽しくても、価格が高く、味や量が日常使い向きではないことから、リピーターが定着せず、徐々に客足が遠のきました。高価格帯と一過性の話題性だけでは、生活の中に入り込むのは難しかったのです。
加えて、全国展開のスピードにも課題がありました。都市部では一定の話題性で集客できても、地方店舗では“歌うアイス”というコンセプトが浸透しきらず、立地選定やニーズとのギャップが顕在化。ローカル市場への適応ができなかった点も、出店戦略としての弱さを露呈しました。
さらに、2014年1月に築地銀だこを運営する株式会社ホットランドの完全子会社となり、そのホットランド社の経営方針転換もあり、次第に店舗数が縮小。地方店舗から閉店が進み、ついには1店舗のみとなりました。
日本人に受け入れられなかった“歌う接客”という体験
コールド・ストーンの代名詞である「歌う接客」は、エンタメ性は高い一方、日本人の消費文化との相性に課題がありました。
注文時に店員が元気よく歌い出す演出は、アメリカでは陽気なサービスとして受け入れられますが、日本では「恥ずかしい」「目立つのが苦手」という声も多く、むしろ心理的ハードルになっていた可能性があります。
実際、SNSやレビューサイトでは「一度は面白かったが、2回目はもういいかな」「歌われるのを待つ時間が気まずい」といった声が多数見られました。中には「静かにアイスだけ買いたかった」というユーザーの声もあり、日本人の“パーソナルスペースを尊重する文化”と正面からぶつかってしまったとも言えます。
企業側がこの文化的ギャップに気づいた後も、歌の有無を選べる仕組みを導入するなどの柔軟な対応は十分に取られなかったように見受けられます。“楽しい”はずの体験が、消費者にとって“気まずい”と感じさせてしまえば、それは逆効果です。文化の違いを読み間違えると、体験型マーケティングも裏目に出るという好例でしょう。
話題性頼みのマーケティングの限界
一発屋に終わるブランドの共通点
話題性だけで集客するモデルは、初回の訪問動機にはなり得ますが、それを越えて顧客を“定着”させるためには、もう一段階の価値設計が必要です。
期待値だけを煽ったブランドは、「一度行けば満足」となりやすく、その後のフォローがなければ自然と足が遠のきます。まさにコールド・ストーンは“初回体験のピーク”を超えられなかった典型です。
このような話題先行型のブームには、「白いたい焼き」「パンケーキ専門店」など、類似の一過性ヒットも見られます。共通しているのは、いずれも“ニュースバリューはあるが、日常に溶け込まない”という点です。特別感だけで勝負するビジネスは、常に新鮮さを更新し続けなければならず、それができないとすぐに飽きられます。
顧客との“継続的な関係性”が作れなかった
顧客維持のためのリテンション施策や、CRM(顧客関係管理)といった地道な取り組みが見られなかったことも、リピーター離れを加速させました。
例えば、誕生日クーポンの配布や、LINE友だち登録によるスタンプカード、会員ランク別の特典など、サーティワンやスターバックスでは多くの“つながり施策”が機能しています。
もしコールド・ストーンがこうした継続的関係構築の仕組みを導入していれば、「また来ようかな」と思わせるきっかけを増やせたはずです。たとえば、月替わりのミックス提案、来店回数に応じた特典、ミニサイズの手軽な商品展開など、リピーターを惹きつける工夫はまだ余地がありました。
他社と比較して見える「成功する戦略」とは?
スターバックスやサーティワンとの違い
スターバックスは「サードプレイス」という概念のもと、日常的に立ち寄れる空間設計を徹底しています。
※「サードプレイス」とは、自宅(ファーストプレイス)や職場(セカンドプレイス)とは異なる“第3の居場所”を意味し、くつろぎや会話が生まれるコミュニティ空間としての役割を果たします。
また、サーティワンは地域限定・期間限定フレーバーなどの多彩なキャンペーンで、リピート理由を生み出しています。
両者に共通するのは「日常に入り込む仕組み」を持っていること。特別な体験よりも、“通いたくなる必然性”が重要なのです。
加えて、両社は「価格帯」「手軽さ」「接客の自然さ」などの点でも、日本人のライフスタイルや心理に寄り添った設計を行っています。つまり、非日常性を持ちながらも“日常の延長線上”にある点が支持されているのです。
体験は“日常に溶け込んでこそ価値がある”
コールド・ストーンのような特化型エンタメ体験は、一度の驚きにはなるものの、日常使いにはなりにくいもの。
サービスが続くためには、日常の中にある“ちょっとしたご褒美”として受け入れられるかどうか。価格、立地、気軽さなど複合的な要素が揃って、初めて顧客は繰り返し利用するのです。
現代の消費者は「体験」に対してお金を払う一方で、その体験が“時間的・心理的に負担にならないこと”も求めています。たとえば、仕事帰りや週末の買い物ついでに寄れるような立地で、気負わず注文できる設計が重要です。